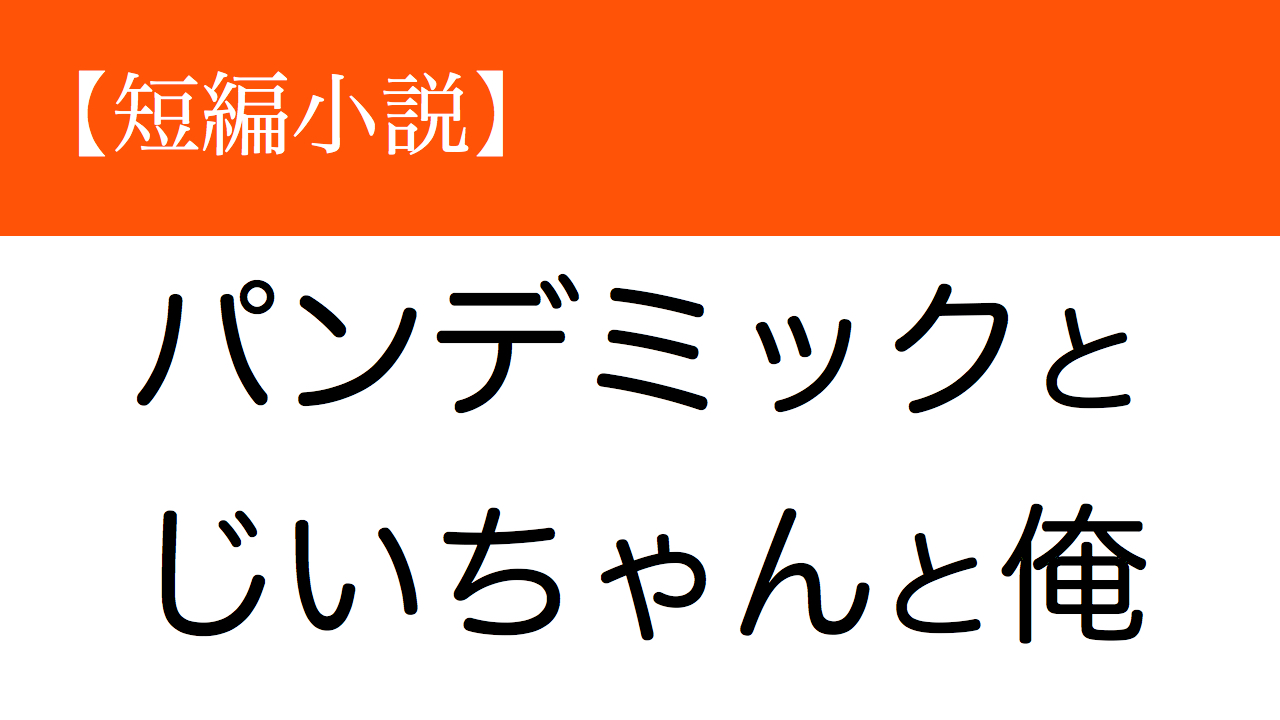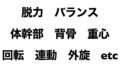※この物語はフィクションです
1.
就職を機に大阪から東京に出てきて一年半。
俺は今、じいちゃんと二人暮らしをしている。
家を探し始めた時期が遅かったからか、なかなか物件を見つけることができないでいると、
東京で一人暮らしをしている母方の祖父から「上京するならウチに住んでもいいぞ?」と連絡があり、
物件探しに疲れていたのと、家賃が浮くのは助かるので、同居させてもらうことにした。
いわゆる居候ってやつだ。
こうして俺は、去年の春からじいちゃんと二人暮らしをしながら、社会人として東京で生活することになった。
仕事は慣れない部分がありながらも順調にこなしつつ、たまには同僚と飲みに行ったり、好きなバンドのライヴへ遊びにいったりする日々。
じいちゃんは出版関係の自営業を営んでいて、今でも家で仕事をしながら、時には麻雀へ、時にはスナックへと、毎日を楽しく過ごしているようだ。
そして二人が休みの日には、じいちゃんと俺は朝から一緒に将棋を指すというのが習慣になっていた。
そんな平和で平凡な日常を過ごす中で、今回のパンデミック騒動が起こった。
2.
今年のはじめくらいから、騒がしいニュースが増えていった。
海外で新種の病原体が発見され、それによる感染症が世界中に広がっていると。
外国では町で突然人が倒れるようなこともあり、感染力も強い上に致死率も相当な高さになるとかで、間もなく世界の保健機関がパンデミック宣言を出した。
日本でも、このままだと何十万人もの死亡者が出るだとか、そんな物騒な話題が世間を駆け巡った。
さらに厄介なのは、高齢者ほど致死率が高くなるという話とともに、若者が感染を広げているというニュースが流れたこと。
病原体を保有している健康な若者が、街に出ることで感染を広げているんだとか。
こんなニュースが毎日流れているうちに、子どもや若者と接することを恐れてしまう大人が増えていった。
職場で仲のいい同僚は、お盆は実家に帰らず東京で過ごしたらしい。
実家の家族から「祖父母が高齢でいつ死ぬかわからないから、今は来ないでほしい」と言われたんだとか。
馴染みの喫茶店で、年配のお客が、子連れの若い夫婦が隣に来たのを見て「席を替えてくれ」と店員に頼んでいたのを見たこともある。
まるで子どもや若者が病原体のような扱いだ。
俺たちは、そんなに危険な存在なのか?
俺たちがいるのは、迷惑なことなのか?
3.
ある休みの日。
俺とじいちゃんは朝から将棋を指していた。
この日じいちゃんは近所の仲間と麻雀に行く予定があるとのことで、一局終わったところで駒を片付けた。
じいちゃんと一緒に暮らしている俺は、最近色んなことを考えてしまう。
じいちゃんは今年88歳、いや、89だったかな?
まあとにかく、この歳で未だに仕事もして麻雀やスナックに遊びにも出かけるくらい元気だが、年齢的には立派な高齢者。
じいちゃんは今の状況を、いや、俺がこの家にいることをどう思っているんだろうか。
「じいちゃんは、俺がここにおっても大丈夫なん?」
「は?なんのことじゃ?」
コーヒーを飲みながらソファで寛いでいたじいちゃんは、きょとんとした表情でこっちを向いた。
「いや、なんか危険な病気が流行ってるってテレビで言うてるやん」
「アホか、テレビなんか大概ウソかヤラセじゃ。周りで誰も死んどらんがな」
じいちゃんは左手に持っているカップをすすりながら、右手をプラプラ横に振った。
「そうなん??あ、でも、健康な若者が病原体を持ってて、高齢者に移してるって言うてるで。高齢者はいつ亡くなるかわからんから、若者と近づくのは危ないって」
「そんなもん、風邪でも肺炎でも一緒じゃ。お前まさか、そんなこと気にして『ここにいて良いか』ってワシに聞いたんか?」
「だって、もし俺のせいでじいちゃんが死んだりしたらイヤやから」
俺がそう言うと、じいちゃんは一瞬険しい表情になったと思ったら「プッ!!」と吹き出し、持っていたコーヒーカップをテーブルの上に置いた。
「何を言うとるんじゃ。人間、歳を取ったら死ぬのは当たり前じゃ。年寄りが死ぬのに誰のせいとかあるかい。
それに、人間は年寄りでも若者でも、いつ亡くなるかなんてわからん。だから毎日を楽しく、今を精一杯生きるんじゃ。
ワシもあとどれくらい生きるんか知らんけど、死ぬまで人生を楽しむだけじゃ。そのためには麻雀とスナックが必要不可欠なんじゃ(笑)」
じいちゃんはそう言って、ガッハッハー!と笑い声をあげた。
「ほな、俺、ここにおってもエエん?」
「当たり前じゃ。お前はワシの孫じゃろ。今さら何を言うとるんじゃ」
<<ピンポーン>>
家のインターホンが鳴った。
「ゲンさん、おるかぁ〜?今日もそろそろ行くべ?」
「おお、もうそんな時間か?おしゃ、ちょいと待ってくれや」
じいちゃんの麻雀仲間が迎えに来たようだ。
俺との会話を切り上げ、じいちゃんは慌ただしく準備をしはじめた。
身支度を済ませ、玄関の扉を開けようとしたその時。
「ワシゃ麻雀仲間はいっぱいおるけど、将棋を指せる奴はお前しかおらんから、ここにおってくれたらワシも嬉しいわ」
じいちゃんはそう言って扉をあけ、いつもの麻雀仲間と出かけて行った。