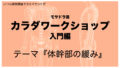ども、こんにちは。高インボムです。
そんなこんなでレッスンで時々話題になり、ブログやツイッターにも何度か書いている『バランス感覚』。
身体操作を考える上でとても重要な要素であり、個人的にはもしかしたら一番大事な要素かもしれないとも思っていますが、この『バランス感覚』というものについて改めて考察してみたいと思います。
『安定』か『固定』か
僕はバランス感覚を語るとき、出す例として『竹馬』と『バランスボール』の二つを挙げることが多いです。
さらに、バランス感覚を養うのに竹馬をオススメする一方で、バランスボールの類はオススメしないというのもしょっちゅう言っています。
僕のレッスンに来てくれてる人は、この話は聞き飽きてるかもしれません(笑)
その理由には自分なりの理論があるのですが、一言で言うと『安定』か『固定』かの違いになります。
『バランス』というものを考える時、それを『安定』と捉えるのか『固定』と捉えるのかがその先の大きな違いになるのですが、安定とは「動きの中で調和を図ること」なのに対し、固定とは「力で一点に留めること」で、全く対極のものだと言えるんですね。
バランスというものが「動きとともにある」のか、「動きとは別である」のか、そういう風にも言えるかもしれません。
また、動きの中で調和を図る安定を目指すためには『リラックス(脱力)』が重要になり、力で一点に留める固定は『緊張(力み)』へと繋がります。
そしてそもそも、身体操作を考える上でなぜバランス感覚が重要になるかというと、「カラダをスムーズに動かすため」というのがあると思います。
つまりカラダの動きや変化が前提になるので、目指すべきは固定ではなく安定のはずなんですね。
竹馬とバランスボール
で、先ほど挙げた二つの例で考えてみると、支点が存在していてそこに対して重心をコントロールする竹馬は『安定』にあたり、支点が存在せず重心を一点に留めることになるバランスボールは『固定』にあたります。
この違いを認識しておくとこの先も何となくイメージしやすいかと思いますが、バランスボールのような「力を使ってカラダを1点に固定させるもの」で訓練すればするほどバランスと動きが別物になり、言い換えるとカラダの固定や緊張(力み)がクセ付く事になり、スムーズなカラダの動きはできにくくなるんじゃないかと思います。
僕自身も色んな方のレッスンをする中で実際にそういう事例を見ているのと、身体操作の指導者で同じような事を言っている人は多いです。
一方で、竹馬をうまく乗りこなすには動きの中での安定を目指す必要があり、歩くのも静止するのも支点や重心など全体を捉えつつ、その中で自分の重心をコントロールする事が大事になります。
また、そのためにはリラックスも重要になるので、動きを前提としたカラダのバランス感覚を養うのに適したアイテムの一つだと考えています。
全体と中心を同時に捉える
なんだかバランス感覚の考察というより竹馬の考察みたいになってしまいましたが(笑)、『動きを前提としたバランス感覚』を僕なりに定義すると、「全体と中心を同時に捉えてそれらの調和を図る能力や感覚」という感じでしょうか。
そしてそれは重心の把握やコントロールにも繋がり、重心の安定のさせ方または崩し方というのはそのままカラダの動きに繋がっていきます。
このように、「動きとバランスがリンクしている」のが本来あるべき『バランス感覚』なんじゃないかなと僕は思っています。
もしかしたら近年見かけるバランス系トレーニングの理論とは真逆になるかもしれませんが、そんな事を思う今日この頃です。
ちなみに竹馬にうまく乗るコツは、自分のカラダの『重心』と竹馬が地面と接する『支点』が縦に揃うようにして、歩く時は足を持ち上げるのではなく、重心を移動させることで足が浮き上がるような感覚を感じられるとイイと思います。
ただ、バランス【感覚】というくらいなので、これもやはり頭で考えて捉えようとするよりカラダや五感で捉えるようにして、理論理屈はそのヒントやガイドくらいに思っておくのがイイかと思います。
要するに、カラダをいっぱい動かしてカラダで覚えようということです(笑)
というわけで、今回は身体操作を考える上でとても重要な要素である『バランス感覚』について、改めて考察してみました。
そしていつもの事ですが、毎回色んなことを言いながらも僕も全てを体現できるわけではないので、これからもまだまだ精進していこうと思います。
では、本日はこれにて。
サラバオヤスミマタアシタ!
※竹馬のレッスンやワークショップのオファー、随時受け付けています。お問い合わせはお気軽にどうぞ!