 心理
心理 【アドラー心理学の誤解】課題の分離は手段の一つであって目的ではない、という話。
ども、こんにちは。高インボムです。 そんなこんなで長年アドラー心理学にハマり続けていて、その理論や技法には何度も助けられ、未だに時間を見つけてはちょこまかと学ぶ日々です。 で、アドラー心理学の話題になると必ずと言っていいほど出てくるキー...
 心理
心理  ドラム
ドラム  カラダ
カラダ 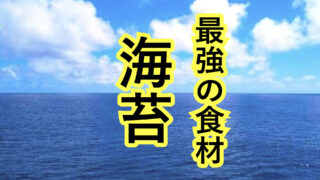 雑記
雑記 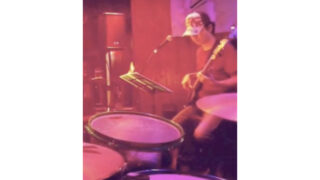 ブログ
ブログ  カラダ
カラダ 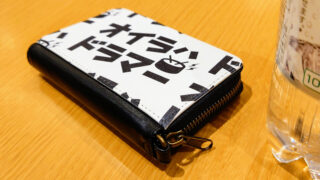 お知らせ
お知らせ 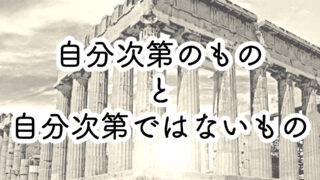 心理
心理  雑記
雑記  雑記
雑記