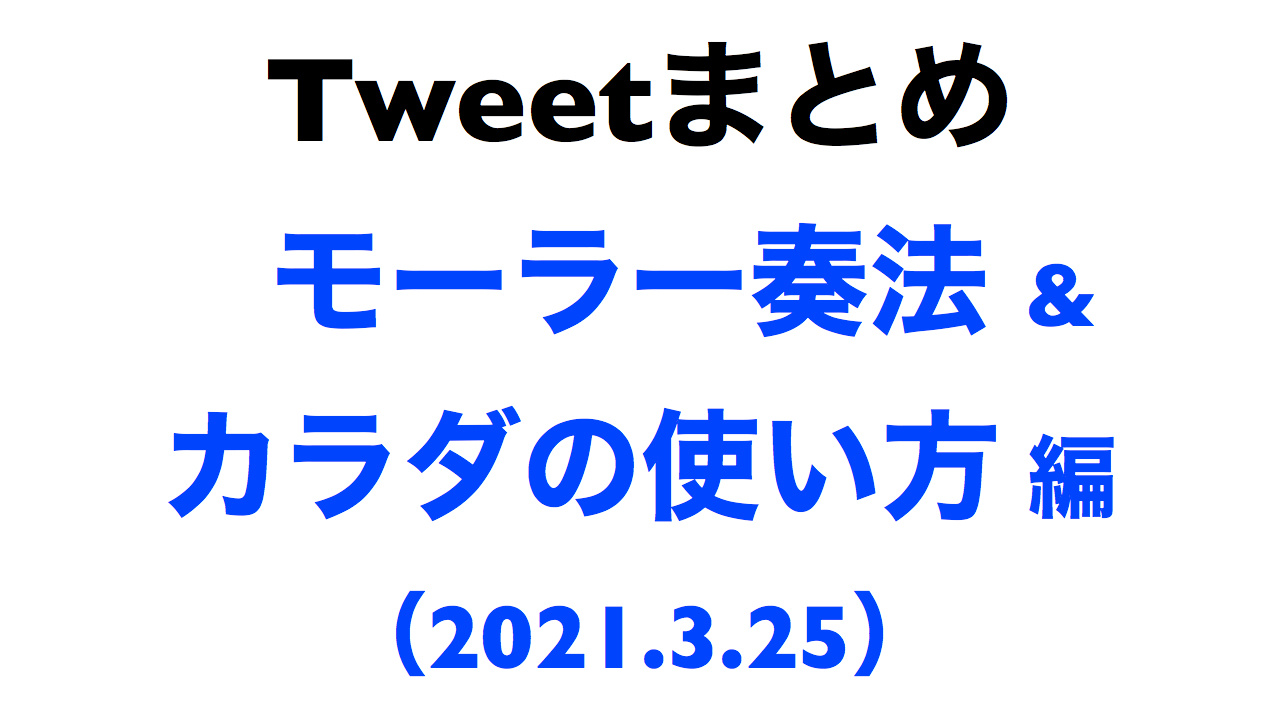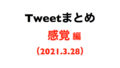ども、こんにちは。高インボムです。
そんなこんなで、ツイッターで時々投稿している『モーラー奏法』や『カラダの使い方』にまつわる話のまとめです。
中国拳法を習っている生徒さんがいて、よく体術の話で盛り上がるのですが
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) January 17, 2021
昔ながらの身体操作理論(特に東洋的な)は、表現は違っても根っこは全部共通してくるのが面白いな〜と
で、全てに共通する部分であり最重要ポイントなのが『骨格でカラダを動かす』ということ
僕もまだまだ勉強中です😺
『かかとに乗せる』
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) January 19, 2021
近代的なスポーツ理論とは多分逆ですが、力を抜いてカラダを使うには踵に体重を乗せるのが大事な時が多々あります
つま先に体重がかかると体の前面が力むのに対し、踵に体重を乗せることでバランスが取れリラックスもできます
抜く動作も容易になってラクに動きやすくなります🙆♂️
野球選手のイチローさん、走塁に関するインタビューで「重心を移動の力に使う」や「足を出すのではなく足を抜くことでスタートする」といった解説をしていて、
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) January 19, 2021
ご自身も一般的な走法や理論とは真逆だとおっしゃっていますが、イチローさんの身体理論は古武術や人体力学の概念に近い部分が多いです🧢
『指を根元まで使う=手のひらを使う』
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) January 23, 2021
物をしっかり持つ時、手のひらも使うとやりやすいです
骨格的には手のひらの下の方まで指の骨があり、それが自然な持ち方だから
逆に手のひらを使わず持とうとすると不自然になります
運転時のハンドルの持ち方をイメージするのがわかりやすいかなと🚲
『股関節の外旋』
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) January 31, 2021
姿勢やリラックスを考察する上で股関節(の外旋)は重要ポイントになります
ヨガやバレエ、古武術系の身体操作でも基本の構えや動作において股関節は重要ですし、
全身の連動や重心移動にも股関節は重要になります
カラダの動きの元を辿ると股関節は重要ポイントの一つかと🦥
ちなみに股関節に限らず、関節のことになると稼動域や柔軟性の話がよくでてきますが、
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) January 31, 2021
個人的にはそれよりもまずは「動かし方」が重要だと思っています(過去にレッスンでも実証)
そのポイントは、
「関節の造りに沿った動かし方をすること」
「根元側から動かすこと」
です🐎
カラダも心も思考も、固定すると倒れなくなるけど動けなくもなる
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) February 5, 2021
安定とはその逆で、動きや変化の中でバランスが整っている状態
柔軟さやバランス感覚をもつこと
倒れる事に怯まず恐れず動きや変化を楽しむこと
大事だな〜🛴
ドラムは手足がバラバラに動いてスゴイね!って言われることがありますが、
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) February 26, 2021
人間だいたいの動きは手足バラバラなので、実は普段の生活から当たり前にやっていたりします(笑)
全身の動きは密接に関わり合っていて、それがうまく繋がると連動するし、繋がりが悪いと干渉しあう、という感じです🕺
全身がうまく連動するためのポイントがいくつかありますが、その一つは下半身の土台
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) February 26, 2021
腰から下の下半身が安定していると(バランスが取れていると)、上半身も力が抜けて、全身の自由度が高くなります
カラダの動きを考える上で、実は下半身はとても大事です🐾
歩く動きを観察するとカラダのことを色々知ることができます
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) March 3, 2021
例えば腕も足もリラックスしてるほど直線ではなく円運動になってたり、
着地する足と腰の位置関係でラクさが変わったり、
股関節の内旋・外旋が重心の移動と関係していたり、
etc
動きの基本は「歩き」の中に全部あるのかもしれません🐕
自転車って、乗れるようになるまでは何度もコケたりしてたはずなのに、
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) March 7, 2021
一度乗れるようになったら乗れなかった時の事がわからなくなるし、再び乗れなくなるって事はほぼない
レッスンで感覚の話をよくするんですが、『感覚でつかむ・覚える』というのは例えばこういう事なんじゃないかなと🚲
動きの練習でジャンプや縄跳びをオススメする事があるのですが、飛び跳ねる動作って気分も良くなります
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) March 11, 2021
とある身体理論では身体への振動が心にも良い作用をもたらすって話もあり、気分を明るく軽くしたい時は飛び跳ねるって結構イイです
ちなみに変なポーズでやると更に効果あります(個人の感想)😄
ドラムレッスンで、スティックをラクに振る感覚を知ってもらうためにボールを投げてもらうことがあります(テニスボール常備してます 笑)
— モサモサドラムスクール/町田のドラム教室・カラダの使い方教室 (@mosa2_school) March 21, 2021
投げる動作(落とす動作)をする時ほとんどの人は腕全体が連動するので、あとはこの感覚をドラムに応用できるとイイのですが、これが意外と難しいです
→
→
— モサドラ/MOSAMOSA DRUMSCHOOL (@mosa2_school) March 21, 2021
ポイントがいくつかありますが、その一つは手放す感覚
スティックを『持つ』とか『叩く』という意識をするほど力が入ったり手先が先行する動きになり、スティックの自由度も奪われるのですが、
ボールを投げる時のように手放す感覚をうまく応用できると腕全体がしなやかに連動しやすくなります🎾
腕を動かす前提で物を持つ時、親指と対になるのが人差し指ではなく中指になるとスムーズに動けます
— モサモサドラムスクール/町田のドラム教室・カラダの使い方教室 (@mosa2_school) March 22, 2021
ペンで文字を書く時や車のハンドル操作をイメージするとわかりやすいかと
親指と中指が対になる事で力まず持つことができ、人差し指が解放されている事で動きの方向をコントロールしやすくなります☝️
また新しい投稿が貯まってきた頃にまとめます。
ひとまず今回はこんな感じで。
サラバオヤスミマタアシタ!